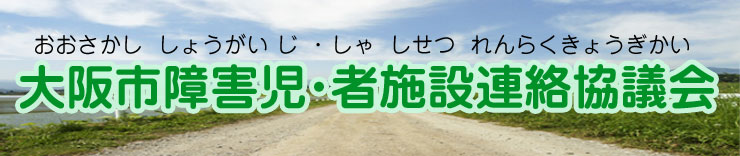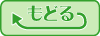アンケートまとめ (・=感想 ★=今後の研修に対しての意見等)
・勉強になりました。もう少し具体的な事例が聞けたら…と思いました。ありがとうございました。
・すごく良かったです。行政に対してどのように訴えていくのか、いけばよいのか具体的な話し会いができる機会も作って欲しいです。そういう連絡会のようなものができれば何もできませんがお手伝いしたいと思います。
・考え続けること、思い続けること、これでいいのか、他に方法はないのか、と、これからもずっと考え続けて行きたいと改めて思いました。
・とても難しい問題だと思いました。私は基本人対人の事なので相手(利用者)の事だけ考えるのではなく職員に対するケアや職員(福祉職)の地位の向上も必要だと思いました。色々考えると、考えれば考えるほど分らなくなってしまいました。難しいですね。
・今日の講義・自己点検チェックシートを行う中で自分自身の対応、認識の甘さを感じた。利用者の気持ちに立って(利用者が不快に感じていないか)自身の対応を見直さなければならないと感じた。また、自分ひとりで考えたり、行動実践するだけでなく、チームで考え合う場、決めたことを周知する方法も同時に行わなければならないと思う。身体拘束、行動制限をせざるを得ない場面もあるが、それを仕方ない、どうしようもないで終わらないようにしなければならないと改めて学んだ。
・現在行われている利用者への対応で身体拘束に繋がる事例がたくさんあり考えさせられる所が多くありました。方法等をあきらめずに考える必要性も実感しました。しかし、本人の危険を考えた事からの方法と、長年家庭で続けられてきた事を考えると経済的負担も考えると難しいこともあると思います。もっと追及していきたいと思います。
・内容は良く分かったが、現場の意見や現状を把握し現場の側に立った意見が聞きたかった。
・今年の4月から障害者施設で働くことになり、不安や戸惑い、疑問がありましたが、今日の学習会で小尾先生のお話を聞き少し理解できたように思います。これを施設に持ち帰り職員みんなで考えていきたいと思います。ありがとうございました。
・大変分かりやすく勉強になりました。“考え続けること”が大事との話、とても印象に残りました。ありがとうございました。
・実例を挙げての説明であり、よく分かりました。事前に質問を取りQ&Aのようなやり方もいいのではないでし ょうか。
・言われることはいたって正しくて心にズキズキくる事ばかりです。ただ現実としてケアが非常に難しい方の対応 では虐待に限りなく近いグレーゾーンの対応が非常に多いと思います。
・支援者側の立場としては、つい言い訳をして理由づけをしてしまうような事例がたくさんあり、より適切な支援 に向けていくための努力を続けていくことの大切さを感じました。虐待や人権侵害は直接的には個々の支援者と 利用者の間で起きることだと思いますが、問題なのはそういった事例がおこる環境があるということで、その環境の改善を常に考えていくことの大切さを考えさせられました。★夕方からの研修で良かったと思います。
・虐待についての再認識と新しい考え方の更新が出来たお話でした。★事例紹介がいくつか入れば良いなと思いました。
・身体拘束、行動制限、虐待について大変勉強になり再確認ができました。施設にて再度職員全体で現状をチェックして防止につなげたいと思います。身体拘束の止むを得ない場合の3つの条件の他に合わせて本人の希望等はどうなるのでしょうか?
・知的障害児施設で働いている者ですが、日々子供たちと接していると言葉遣いであったり接し方が乱暴になってしまうことが良くあります。そういう時には今日の講義を思い出し、子どもの立場に立って考えていきたいと思います。
・今日お話しを聞けたことで自分の対応の見直しの機会を得られ、良かったと思います。
・「虐待」と一言でいっても行為だけで定義は出来ない、それを受けた当事者の思いが大切ということを改めて考えさせられました。支援する上でその支援を「これしかない」「仕方ない」で終わらず、検討を重ねるという事、他の施設と共有すること、また基本ですがニーズ、アセスメントの大切さを実感しました。
・自己点検のチェックシートでは、自信を持って答えられない箇所があり、見つめ直さない点を改めて確認できました。拘束問題は最近よく耳にしますが、施設の体制や建物など、課題の多い問題だと思いました。虐待問題は特に心理的虐待に気を付けたいと思いました。会話の中で生じるので、言い方次第で無くすことができると思うし、気配りをして行きたい。「適切なケア」心がけたい。家族や本人に説明をする事の大切さを改めて認識できました。★目指す姿の確認できたので、具体的な支援方法等を学習したい。他施設の実践(成功)方法等。
・新聞沙汰になった学園は同じ法人で今日のことで私たちの施設でも何度も討議したり考えてきました。そういう意味では今日の研修はまさにリアルタイムでした。でも現場にいてだったらどうすればいいの…そしたら泊まり勤務等は仮眠もとらずに対応しなければいけないの?等様々な疑問点も浮かんでいるのも事実です。けれど先生のおっしゃった、“常に考え続けること”を頭に置いて気分をあらためて勤務に就きたいと思いました。
・未だに「これが虐待?」と疑問を持つ対応がありますが(現場として)、大事な事は常に未然防止を心がけ、百人百通りのケアに対して一人ひとりが考え続けることが大事なんだと思いました。持ち帰り周知に努力したいと思います。
・本やネットにはたくさんの事例がある。施設職員はたくさんの事例と、自分の施設の利用者に重ねる想像力が必要だと思う。日々変化する状況で職員は考えていくことが大切だという最後の言葉が印象的でした。何に関してもPlan,Do,See が大切だと思った。
・利用者の思いをどこまで受け止めきれるかという問題にどの施設も直面していると思う。自立支援法になり、良くも悪くも利用者個人の願いがクローズアップされるにつれ、通所、入所における「集団生活」「健常者と同様の社会的生活」「発達支援」との乖離が起こっているようにも思います。
・日々利用者支援業務を行う中で、適切な支援だったのか最善策だったのかと思い悩むことが多いです。今日の講演を聞き「虐待の判断基準は利用者本人の気持ちを考える」という言葉を持ち帰り現場での自分の行動を振り返ってみたいと思います。
・多くの事例を見た中で、明らかに虐待と思われるものもあれば普段何気なくやってしまっているかもしれないなと思う内容もありました。日々「考え続ける」という事を頭に置き、より良い支援をして行きたいと思います。
・不適切だと思えるような事でも慣れるという、マヒするというが、時間がたてば当然とまではいえないが当たり前のように不適切ではないように思えてしまっている事が多々あるように思います。考え続けることの大切さを改めて痛感しました。
・虐待という言葉については常に頭の中で意識しながら仕事をしているつもりであるが、日々の支援、関わりの中で抜けている所があると思う。自分自身の意識も大切だが、本当に職員同士が指摘し合えることが大切なのかなと感じました。
・不適切なケアという事をもっと深く考え、何が適切なのかを考えていきたいと思います。
・教科書的内容で“ワカッテイル”話だった。もっと生々しい、現場の戦いの中から絞り出されたような話が聞きたかった。
・わかりやすく説明していただき再確認できた。100人いたら100通りの支援の必要性が改めて知らされた。
・改めて勉強になりました。常に行動、業務などチェックしていきたいと思います。職場全体で頑張って取組みます。★マニュアル作成
・私の職場が通所施設で平成13年の手引書に見られるような事が全くなく、利用者、家族からの苦情の事例に関しても殆ど該当する事柄はありませんでしたが、何故に深みに落ちる落とし穴があるか分からない。職員の側からしてはほんの小さなことや言葉でも、利用者本人やご家族に不愉快な思いや苦情を与える可能性があるので常に意識を持って従事して行きたいと思います。
・おもしろくなかった。★講師の方がただ話すのではなく、参加型だともっと踏み込んで聞けたと思う。
・虐待防止法や権利条約など障害者の方への施策の流れに、施設や職員等へのバックアップシステムが整備されていない。施設入所者の重度化が進んでいく中、強度行動障害などの対応困難なケースも多くなっている。施設職員は虐待や身体拘束などに意識し襟を正すべきところは正していくべきであるが、人員配置基準の少なさ(勿論報酬単価の低さ)といった要因もある。行政側は支援技術の未熟さと言い放つだけだが、ではその支援技術が未熟な施設に対して行政としてどのようなフォロー、バックアップをしてくれるのか。現場の状況に対してどのような対策を講じてくれるのかという部分に疑問を投じたい。
・教科書の授業を受けたような気分。もっと踏み込んだ心に響くようなものだと勉強になったと思う。★もう少し早い時間にあれば良かった。終了時間20:00は遅い。他施設で起こっている問題についてグループで話し合えたらおもしろい、勉強になると思う。
・改めて虐待(身体拘束など)の抱える問題の多様さに気付かされました。先生が最後に言われていた対人関係という言葉、納得もできました。身体拘束の現状やその悩ましい問題についてもう少し語っていただければさらに良かったかと思います。
・今日の学習会を受けて自分の中でも振り返り、施設全体としては「個別対応としては」など色々なことを考えされられました。明日からもこの学習会の件についても全体で感じたことなど話し合いたいと思います。本日はありがとうございました。
・虐待について再度意識確認をすることができたのではないかと思います。次回はなぜ人は虐待をするのか、又、具体的な技術を身に付けることが大事であると言われていましたので続けての研修をお願いしたいと思います。
・普段自分が当たり前のようにしている支援に対してそれで良いか、利用者さんはどのように感じているのか、等を見つめ、考えなおす良い機会になりました。
・大変貴重なお話を聞かせていただきました。最後にまとめていただきました7つの項目(太字)はとても大事だと思いました。明日から支援に役立てていきたいと思います。
・私は全く未経験の福祉業界に飛び込んで2か月が経ちましたがまだまだ未熟だし素人同然だと痛感しました。今回の研修でどこからどこまでが虐待なのかすごくためになりました。私は障害者の就労支援の施設に勤務していますが虐待まではいかないのですが(叱り方、指導)もし1つ間違えたら虐待につながる状況にある時があったような気がしましたので今回の研修を参考にして今後の勤務に役立てたらというか役立てていかないといけないとつくづく思いました。
・支援を行っている上で虐待につながっていると思ってはいませんが、常に利用者が満足しているサービスを行えているとは思えないことがあります。「気になる」「悲しい」「不快」と感じる適切といえないケアをより良いものにしていくことが大切だと思いました。説明すること、相談することが大切だと思いました。ありがとうございました。
・利用者本位という大原則を忘れず、支援していくことが大切だと思った。また日々の自分の支援を振り返り、自分の考え方等を押しつけたりしていないか、利用者に合わせた対応をしていきたいと思いました。
・自分の行っている日常的なケア、支援というものが果たして適切であるものか、考え直す良い機会になったように思います。★今後の福祉施策(民主党政権になった辺りで)
・自己点検チェックリストは日頃の作業に必要だと思います。
・研修を通じて日々の支援の根底に一人ひとりの権利擁護や人間の尊厳というものをしっかりと心に留めることの大切さを再確認させて頂きました。今回の内容を自分自身しっかりと現場に持ち帰り、日々の支援や関わりを振り返り、利用者、家族の立場に立った支援、より良い、気持ちの良い支援を思い描き続け、目指していきたいと思います。ありがとうございました。
・具体例の振り返りを丁寧に行って下さり、実践と重ねて考えられました。しかし要因の掘り起こしや防止に対する構えについての方が流れるような話しだった事が残念でした。グレーゾーンに対してどう捉え、議論する為の力をつけていきたいです。★見て分かりやすい、身体への虐待に加え、知的障害者への対応における働きかけに対する虐待についての学習会を詳しくして頂きたいです。
・大変参考になりました。今後の支援に生かしていければと思います。施設運営に関して理念や運営方針の周知徹底が必要だということが非常によく理解できました。支援員のコミュニケーションの大切さも重要だと痛感しました。
・普段行っている支援の方法を何度も見直し、固まった考えに縛られないことが虐待を、虐待に繋がる支援方法を防ぐことに繋がるということが分かりました。対人関係である以上100人いれば100通り、利用者が日々の生活を有意義に暮らせるようにちゃんと説明できているか配慮ができているか、自分自身しっかり勉強していかなければならないなと思いました。
・今回の研修で日々の業務を改めて見直すことができて良かったです。身体拘束の問題は大変難しく他利用者の安全面を考慮すると止むを得ずという場面もあります。そんな時は職員の人手不足を痛感します。
・平成14年に入所施設における身体拘束について発表したことがあります。当時既に老人関係で拘束の3要件も出されており、それにならって考えていく必要があると提案し障害施設としての苦しみも皆さんに正直に打ち明けました。ところが何故か当時は反応が乏しかったです。時間が経って今日他の施設(特に入所?)からその苦しみの声が聞けて妙に納得した気分です。会場からの意見もあったように生活(命)を預かる者としてマンパワーではなく他の方法で拘束をクリアーできるなら是非その方法を知りたいです。★児童は市の虐待マニュアルがあり、通報や調査システムが確立されています。障害特性に合わない部分もあり苦慮するところです。者の虐待防止法が制定されれば恐らく大人の施設でも同様の事が起こり得ると思います。
・職場内の人間関係が良好な状態であることが大切だと(民主的な職場)思います。利用者や家族が安心して不満などを言える施設であること、不適切な支援は100%なくならないのではと思いますが、それに近付けるように努力していく、そんな姿勢が見られる施設でありたいと思います。 本日の研修に職員自らが行きたいと行動してくれたことを喜んでいます。この力を支えにさらに日々努力していきたいと思いました。(管理者より)
・普段、気に掛けていないところもあったので、改めて確認できてヨカッタ。サービス従事者として、世間で問題になっている虐待は、人ごとではないと思った。グレーゾーンはやはり周りから見ても分かりにくかったり、当人も気付いていないことも多々あるのでは〜、と考えると、やはり、客観的な立場からの視点は必要不可欠であると思う。
・虐待というものを今まで見た事がないと思っていたが、自分では気付いていないだけで虐待もしくは虐待というまでではないが利用者に不愉快を与えるような言動をしている可能性もあるかも知れない。自身の日々の関わりを見つめなおす事が大切だと思った。また、どういったものが虐待なのか、更に学びを深めなければならないと思った。チェックリストなどで自身を振り返り易いものを作成することも必要。
・今日の学習会は大変勉強になりました。今日の事を教訓として大いに活用しようと思います。
・虐待でもなく適切でもない空間は一歩間違えば虐待につながってしまうので職場に戻って他の職員とも話しあって行きたいと思いました。
・実際の事例からもう1度施設内で行われていないか、またしないようにするために考える機会を作る必要があると感じました。この位ならと思うグレーゾーンが多々あるのが現実だと思います。これをどのようにクリーンにしていくのかをこれからの課題にしていきたいと思います。★何度もこういう研修を行うことで更に自信をスキルアップ。お客様への生活の質の向上にもつながるので、どんどん行っていただきたいと思いました。
・一つひとつの事例を丁寧に説明して頂いたことで自分の中でじっくりと振り返ることができました。現在マニュアル化を進める上で施設の現状、自分たちの支援をまず振り返ってもらう取り組みをしています。先生の口調、ペース参考になりました。今はアンケート形式でしていますが、直接コミュニケーションを惜しまず、一緒に考える機会を持とうと思ってます。ありがとうございました。
・一つの見解として参考になりました。偏らず、ニュートラルに現状を考えたいと思います。★回を重ねながら、しっかりと学習したいです。(次回も機会があれば…)
・今までの自分の利用者さんへの対応を見直すきっかけになりました。
・色々と参考になりました。今後益々改善されるようにお願いします。
・日々の仕事を振り返る良い機会になりました。虐待の事例は重さを感じました。職員の意識向上により防げる虐待や適切な支援が増えることと思います。その一方で例えば拘束に代わるものとして職員の見守り、援助が必要かと思います。それも複数。そのようなケースが現場には重なって存在します。職員の大幅な増員こそが本当の意味での防止となるのではと私は思います。私も声を上げますが、皆さんと共に頑張りたいと思います。
・もやもやと考えていたことをはっきりと文字化、言語化しておられると思いました。ただそれを施設内で実行する場合、やはり管理側は「やっておけ」、スタッフ側は「時間もないから放っておこう、やったと言っておこう」ということになりがちだと思います。会議などで何かのついでに議題にするだけでたいして話し合われず、主題として扱う時は、何か取り返しのつかない問題が起きた時になるのではないか、と感じました。「議論をしなさい」「しましょう」と言うのであれば、せめて立ち会うべきだと感じます。それに対して「時間がない」「人がない」では、同じことを言っているだけに思えます。★実際職員されている方も話していただきたいです。
・身体拘束、行動制限についてのお話でしたが、当事者の思いが一番大切。思いを大切にし、思い続けられるよう努めたいと思います。
・今日の学習会で日頃の自分の支援を振り返ることができました。自分にとって意味のある学習会であったと感じています。考え続けることの大切さを改めて感じました。ありがとうございました。
・日々の対応に満足せずに「課題があると思い描き続けること」は大事だと思いました。又、目に見える身体拘束だけではなく、支援の在り方を見直すこと、見直しを継続していく視点の大切さを思いました
・虐待防止について、技術やサービス云々で変わるのか?思想が大切だと思う。★又機会があればよろしくお願いいたします。
・障害者虐待にはいくつかの種類があり違法行為で…これは生きている以上生きている人全員にやってはいけない行動だ!と思っていますが、なかなか言葉で分けられない小さな虐待を、血の繋がった子どもにさえしていたのかもしれないと考えさせられました。支援者としても当たり前のことでも、支援者以外にもあたりまえのこの基本的な(お話から得られる)ことを世界中の人に伝えていけたらいいなぁーと感じます。正解は一つではない!という部分で内心私は救われました。ありがとうございました。★基本的なお話から今回は聞けましたので次回から現場の声や例を出したお話をお願いしたいです。実際、現場の現状を体験している方の大変さを語るような学習会や研修をして欲しい。
・毎日の仕事の中で「わかっている」と思っていても、こうして学習会で改めて文章として目にすると基本的な部分から崩れている気がしました。虐待は「いけないこと!」とわかっていても、その時の自分の精神状態や置かれている立場などに左右され虐待に繋がりそうな時があります。知識のなさが虐待に繋がる…とお話にありましたので日々スキルアップに努力したいと思います。★本当はもっと具体的な事例をたくさん聞かせてもらえると思って参加しました。「こんなことあったけど、こんなふうに乗り切れました。…」みたいな話を聞いて自分の職場に置き換えて活用できるかと思ってました。知的障害者の職場なので知的障害限定の研修をして欲しいです。
・分かり易く丁寧にお話し下さり良かったです。ご家族とのやり取りの中での説明不足、配慮不足によるトラブルに繋がることも大いに参考になりました。考え続けることの重要性、実践していきたいです。ありがとうございました!!また、良き研修会をお願いします。★事例(実際にあった)を聴き、共感、学びをしていきたい。